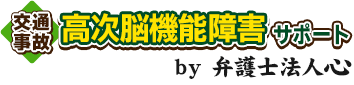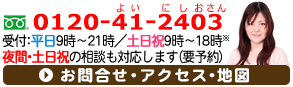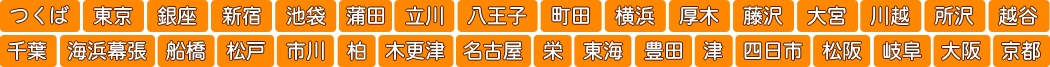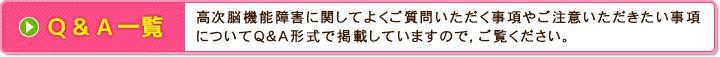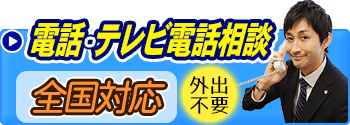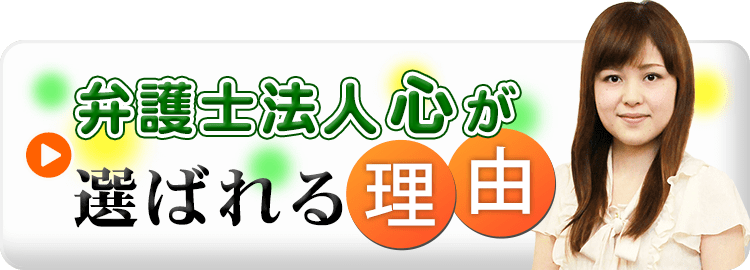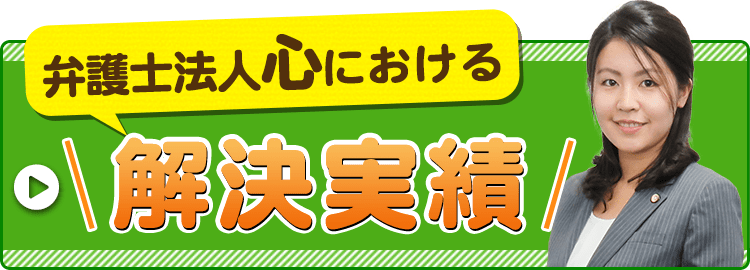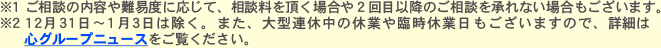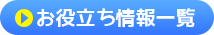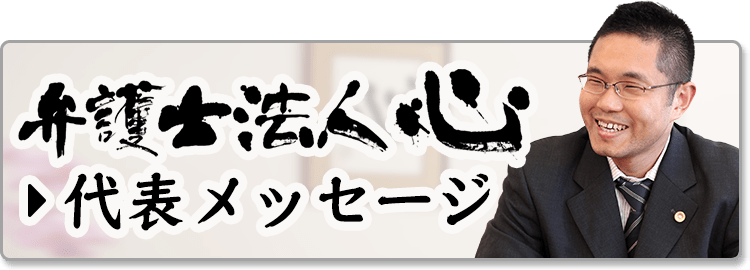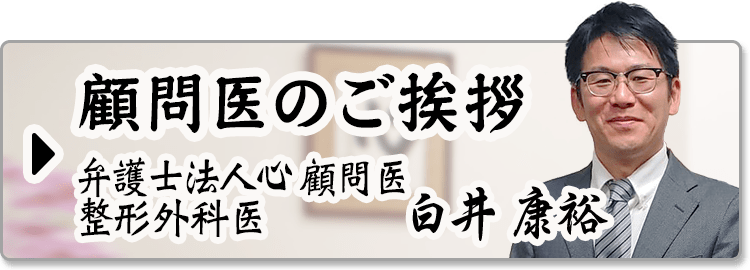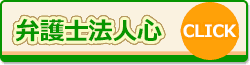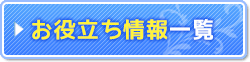「東海地方にお住まいの方」向けのお役立ち情報
津で高次脳機能障害について弁護士への相談をお考えの方へ

1 津にお住まいの方のご相談は当事務所へ
津やその周辺にお住まいの方が相談に訪れる際に便利な駅近くに事務所を設置しています。
弁護士法人心 津法律事務所の最寄り駅は津駅で、駅から0.5分の場所に事務所がありますので、電車でのアクセスが良好です。
高次脳機能障害の電話相談にも対応しておりますので、来所が難しいという方は、電話相談をご利用ください。
弁護士の顔が見える形での相談を希望される場合は、テレビ電話を用いて対応させていただきます。
まずは初めてのお客様専用のフリーダイヤルまたはメールフォームからご連絡ください。
受付担当のスタッフと相談日時の調整等をさせていただき、調整した相談日時に弁護士と相談するという流れになります。
2 高次脳機能障害を相談する弁護士を探す際のポイント
交通事故による高次脳機能障害については、特に専門性が高いため、正確な知識を持っており、高次脳機能障害の後遺障害等級申請等について適切なサポートやアドバイスをしてくれる弁護士を選ぶことが大切です。
高次脳機能障害に詳しい弁護士の見極め方についてはこちらをご覧ください。
後遺障害等級は損害賠償金額に大きく関係してくるため、適正な等級認定を受けることが、適切な損害賠償につながります。
交通事故後、早い段階から適切なサポートをしてくれる事務所であれば、依頼者の方は安心して通院を続けることができるかと思います。
当法人では、交通事故を得意とする弁護士らを中心にチームを作り、そのチームの弁護士が高次脳機能障害などの問題解決にあたっていますし、内部研修を行う等、日々研鑽を積んでいます。
適正な等級認定と適切な損害賠償を受けられるように尽力いたしますので、お困りの方は、お気軽に当法人にご相談ください。
3 高次脳機能障害の損害賠償について
相手方保険会社から示談金が提示されたが、示談に応じていいものか悩んでいるという段階で、弁護士をお探しの方もいらっしゃるかと思います。
当法人では、そのような方が少しでも気軽に相談できるように、妥当な損害賠償額を無料で算定するサービスを行っています。
妥当な損害賠償金額を把握してから、実際に弁護士に依頼するかどうかを決めていただけますので、どうぞお気軽にご利用ください。
高次脳機能障害の損害賠償金は高額になる場合も少なくありませんので、少しでも不安に思うことがありましたら、示談に応じる前に一度弁護士にご相談ください。
4 弁護士費用
すべての保険会社の弁護士費用特約をご利用いただけます。
保険会社から弁護士費用の支払いを受けることができるものになりますので、弁護士費用特約が付いているかどうかを一度ご確認ください。
これがない場合であっても、交通事故について原則無料でご相談を承っておりますので、どなたも気軽にご相談いただけます。
豊田で高次脳機能障害に関して弁護士をお探しの方へ 四日市で高次脳機能障害について弁護士に相談したい方へ
津の事務所について
当法人は多くの方にご利用いただきやすいよう、津駅の近くに事務所を設けております。駅から歩いてお越しいただけますので、お気軽にご相談にお越しください。
高次脳機能障害となった場合の示談の時期
1 高次脳機能障害となった場合の示談の時期

交通事故に遭い、高次脳機能障害となった場合、障害が将来にわたって残る場合が多く、障害の程度も就労ができなくなったり、介護の必要が生じる等、重い場合が多いです。
従って、高次脳機能障害によりどの程度の損害が生じているのか明確化したタイミングが適切な示談の時期と言えるでしょう。
具体的には、症状固定となり、後遺障害等級が決まった時期が示談するのに適切な時期と言えます。
2 高次脳機能障害の症状固定時期
交通事故で高次脳機能障害となった場合、症状固定時期は見極めが難しいことが多いです。
症状固定とは、これ以上治療をしても改善が見込めない状態をいいます。
高次脳機能障害での治療は、脳機能の回復の点はもちろんのこと、身体的な麻痺などの症状が生じていることも多いです。
そこで、身体的機能のリハビリの状況も考慮する必要があります。
また、被害者が学生だったり、仕事をしている場合には、学校や職場での生活状況をみて、周囲となじめているか、なじめていないのであれば環境をどのように調整すればよいのかなどを検討しなければなりません。
就労訓練に通っているケースもあります。
このような様々な事情を考慮して、症状固定時期を判断しなければなりません。
3 後遺障害等級の決定
症状固定となったら、後遺障害の申請をすることとなります。
申請先は加害者の加入する自賠責保険です。
自賠責保険において高次脳機能障害の場合に認定されうる後遺障害等級は、1級、2級、3級、5級、7級、9級です。
最も重い等級は1級で、日常生活において常時介護を要するものです。
2級は要介護の度合いは1級ほどではありませんが、日常生活において随時介護を要するものです。
3級以下は、直接的には要介護状態にあることは求められず、労務に対する制限の度合いによって等級が分けられます。
終身労務に服することができないものが3級です。
後遺障害等級が認定され、等級が決まれば、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料などは各等級に応じて算定されるため、その金額を算定することが可能です。
また、1級や2級の場合は要介護状態になったことが前提の等級ですので、将来の介護費も認められるのが通常です。
このように、後遺障害等級が決定されれば、賠償金の算定が可能になるため、示談ができる可能性が出てきます。
4 弁護士に相談を
上記のように、交通事故により高次脳機能障害が残った場合、症状固定となり、後遺障害等級が決定すれば損害額を算定できますが、結局は相手方が認めなければその算定に従った賠償金を獲得することはできません。
そして、高次脳機能障害が残った被害者自身はもちろんのこと、その家族も法律的なことは素人であるため、加害者保険会社を説得し、適切な金額を認めてもらい、示談にこぎつけることは容易ではありません。
そこで、高次脳機能障害が残った場合は後遺障害の申請、その後の示談交渉を弁護士に依頼することを強くお勧めします。
弁護士法人心は、高次脳機能障害の示談についても多数の実績がございます。
津で交通事故に遭い、高次脳機能障害が残った場合は、弁護士法人心 津法律事務所にご相談ください。
高次脳機能障害の逸失利益の金額と支払方法
1 後遺障害の逸失利益とは?

交通事故に遭い、高次脳機能障害の後遺障害が残った場合、将来にわたり労働能力の低下が残存するのが通常です。
そこで、高次脳機能障害により後遺障害等級が認定されれば、後遺障害等級に応じて、将来にわたる労働能力の低下による収入分の減少が賠償されます。
これが、後遺障害逸失利益です。
2 後遺障害逸失利益の金額
後遺障害逸失利益は、基本的には、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で算定します。
基礎収入額は、原則として、事故当時の現実収入額により算定します。
次に、労働能力喪失率についてです。
高次脳機能障害が後遺障害として認定される場合、1級、2級、3級、5級、7級、9級のいずれかとなりますが、自賠責保険では各等級について、次のとおり労働能力喪失率を定めています。
1級~3級 100%
5級 79%
7級 56%
9級 35%
労働能力喪失期間は、症状固定時から就労可能年限である67歳までとされるのが原則です。
3 後遺障害逸失利益の支払方法
これまでは、後遺障害逸失利益が支払われる場合、将来にわたり発生する分も和解時あるいは判決時に一括で支払われることとなるため、中間利息を控除して計算する方法が慣行となっておりました。
具体的には、ライプニッツ係数を用います。
これに対し、令和2年7月、後遺障害逸失利益について定期金賠償を認める画期的な最高裁判例が出されました。
この最高裁判決は、後遺障害逸失利益について、実際の取り分が大きく減る一括払いではなく、将来にわたり、毎月(あるいは毎年)定期的に受けとる定期金賠償の形で支払いを受けることを認めました。
ただ、実際には、定期金によるのか、一時金によるのかは、ケースごとに慎重な検討が必要になりそうです。
なぜなら、定期金賠償のほうが、被害者が受け取れる金額が増えますが、被害者は、定期的に症状や収入状況に変化がないか、加害者側(保険会社等)から接触を受け続けなければなりません。
この負担ないしストレスは相当なものでしょう。
また、加害者側から、症状が回復したのではないか、収入を得ているのではないか等と主張され、後に減額されるというリスクもあります。
いずれの支払い方法が良いのかは、よくよく弁護士と相談しましょう。
4 弁護士法人心にご相談を
津で交通事故に遭い、高次脳機能障害が残り、弁護士をお探しの方は、一度弁護士法人心 津法律事務所にご相談ください。
高次脳機能障害はお早めに弁護士にご相談を
1 適切な後遺障害等級の認定

高次脳機能障害は、適切な後遺障害等級の認定が受けられるかが極めて重要です。
自賠責保険で認められる高次脳機能障害の後遺障害等級は、1級、2級、3級、5級、7級、9級に分類されます。
そして、賠償金額は等級に応じて算定されるため、等級が変われば金額は大きく異なり、数百万円単位、場合によっては数千万円単位で変わることもあります。
2 後遺障害慰謝料
赤い本(公益社団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」弁護士基準)によれば、後遺障害慰謝料は、後遺障害等級が第1級の場合は2800万円、2級の場合は2370万円、3級の場合は1990万円、5級の場合は1400万円、7級の場合は1000万円、9級の場合は690万円とされています。
3 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益の算定の際、労働能力喪失率が何パーセントかで後遺障害逸失利益の金額が大きく変わりますが、1級、2級、3級の場合は労働能力喪失率は100%、5級の場合は79%、7級の場合は56%、9級の場合は35%とされております。
4 将来の介護費
高次脳機能障害が残り、介護が必要な場合は、要介護状態であることが念頭におかれた等級である1級や2級であれば、将来分も含めた介護費用が支払われますが、3級以下では、要介護状態であることが念頭に置かれていないため、介護費用まで支払われることは難しい場合があります。
よって、ここでも等級が重要と言えます。
5 事故後なるべく早く弁護士に相談すべき
このように、高次脳機能障害が残りそうな場合には、適切な後遺障害等級の獲得が極めて重要ですが、適切な後遺障害等級を得るためには、事故直後から適切な行動をとっているかが重要になります。
事故直後から適切な検査等を受け、適切な医療機関で治療を受け、医師とコミュニケーションをとり、家族などの身近な人が見守ったうえで必要なことを記録するなど、必要十分な材料をそろえていく必要があります。
早期に弁護士に相談していれば、このような点について、早い段階から弁護士からアドバイスを受けることができます。
また、場合によっては、保険会社とのやり取りを円滑にするため、早期に弁護士が介入しておいた方が良い場合もあります。
そこで、津及びその近辺で交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ることが判明した方は、なるべく早めに、弁護士法人心 津法律事務所にご相談ください。
高次脳機能障害と将来の介護費用
1 高次脳機能障害で将来の介護費用が認められる場合

交通事故に遭い、高次脳機能障害が残り、介護が必要となった場合、将来にわたって介護費用がかかります。
介護の業者に頼まなければならない場合は当然ですが、家族が介護をする場合も家族にとって介護は相当な負担です。
このように、介護を要し、自賠責保険の後遺障害等級別表第1の1級、2級に該当する場合には、将来にわたって発生する介護費用を相手方に請求することができます。
自賠責保険の後遺障害等級別表第1の1級は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」、同2級は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」です。
上記別表第1の1級と2級は要介護であることを念頭においた等級です。
これに対し、別表2の1級~14級の各等級は、必ずしも要介護状態にあることを念頭においておりませんので、将来の介護費用が当然に認められるわけではありませんが、一定の場合には認められます。
本稿の記述は、別表第1の1級、2級に該当する場合を念頭においております。
2 将来の介護費用の金額は?
「介護日額×平均余命までの期間(中間利息を控除)」にて計算されるのが通常です。
そして、介護日額は、職業介護者による介護を前提とする場合は、実費で算定することが通常です。
また、在宅介護か施設介護かによっても異なります。
介護の業者から見積もりを取る等で金額を立証することとなります。
通常、職業介護の方が親族介護の場合と比べ、日額は高額になります。
親族等の介護の場合は介護の度合いに応じて異なりますが、常時介護が必要な場合は、8000円~10000円程度、常時介護までは必要ない場合は減額されることが多いです。
3 実際の認定例
実際の事例では、上記の要素を組み合わせて認定される場合が多いです。
例えば、平日(週5日)は職業介護者により、休日(週2日)は近親者による介護による、近親者が介護困難となる67歳となった後から被害者の平均余命までの間は、主として職業介護人による介護が行われる蓋然性が高いとして職業介護者によるとして算定をした例、症状固定からしばらくの間は入院付添介護、その後両親による介護可能な間は両親による介護、両親死亡後の被害者の平均余命までは施設入所介護をベースで算定した例等があります。
4 弁護士にご相談ください!
高次脳機能障害を負った交通事故の被害者が介護を要する場合、適切な将来の介護費用が認められるか否かは、被害者の今後の人生を左右するほどの重要な問題です。
適切な金額を獲得するためには、どのような介護が必要なのか、その費用はどの程度必要なのか、適切に主張し、証拠となる資料を収集しなければなりません。
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ってしまい、将来の介護が必要となった場合は、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
津や津近辺の方であれば、弁護士法人心 津法律事務所にご相談ください。
高次脳機能障害と後見制度支援信託
1 後見制度とは?

交通事故後に高次脳機能障害が残ってしまった場合、被害者の方の判断能力が低下し、それゆえに自分で財産を管理したり、必要なサービスについて契約を締結したりすることが出来なくなってしまうことがあります。
このように、被害者本人の判断能力が低下してしまった場合に、本人を保護し、支援するための制度を「後見制度」と言います。
2 後見制度支援信託とは?
⑴ 後見制度支援信託の趣旨
後見制度を利用する場合でも、後見人が必ずしも本人の財産を適切に管理できるとは限りませんし、後見人が本人の財産を浪費したり横領したりする可能性も否定できません。
そこで、本人の財産を保護するために設けられたのが、「後見制度支援信託」という制度です。
⑵ 後見制度支援信託の概要
後見制度支援信託とは、後見制度による支援を受ける本人の財産の内、一部を預貯金のまま後見人が管理し、その他の通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことを言います(なお、後見制度支援信託が利用できるのは「成年後見」と「未成年後見」のみであり、「保佐」、「補助」、「任意後見」の場合は利用できません。)。
後見制度支援信託を利用すると、信託された金銭は信託財産として受託者である信託銀行が管理することとなり、財産信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書が必要となります。
このようにして信託財産の管理に家庭裁判所のチェックを必要とすることで、本人の財産を保護するというのが後見制度支援信託の仕組みです。
3 ご家族に高次脳機能障害が残ってしまった場合は弁護士にご相談を!
交通事故被害者の方に高次脳機能障害が残ってしまったという場合には、後見制度の利用が必要となる案件が少なくありません。
そのため、ご家族が交通事故に遭い高次脳機能障害が残ってしまったという場合には、交通事故と後見制度に詳しい弁護士に一度相談をしてみることをおすすめいたします。
高次脳機能障害で認定される可能性のある後遺障害等級
1 高次脳機能障害と交通事故の後遺障害

高次脳機能障害が交通事故の後遺障害として認定される場合、次の等級が認定される可能性があります。
- 9級 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
- 7級 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
- 5級 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
- 3級 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
(以上が自賠責後遺障害等級別表第2)
- 2級 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
- 1級 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
(以上が同別表第1)
2 認定される等級によって賠償金が大きく変わります
以上のとおり、高次脳機能障害が生じてしまったとしても、その重症度に応じて、認定される等級は様々です。
等級によって、慰謝料額、逸失利益を計算する際の労働能力喪失率、将来の介護費用の認定額等が変わってきます。
等級が違うと、数千万円単位で賠償金が変わってくることも少なくありません。
3 弁護士に相談しましょう
高次脳機能障害を負ってしまった方が適切な後遺障害の等級を獲得するためには、事故直後から適切な医療機関にかかっていたか、適切な検査や治療を受けていたか、後遺障害申請の際適切な資料を収集・提出できたか等が重要になります。
しかし、高次脳機能障害を負ってしまわれた方は、記憶力や集中力が低下する、怒りっぽくなる、会話がスムーズにできない、文章がうまく書けない、理解力が低下する等の変化が生じていることが多く、このような状態で後遺障害の申請等を行うのは、極めて難しいと言えます。
そのため、実際には被害者のご家族や身近な方が、通院や資料の収集を行うことになります。
とはいえ、被害者の周りの方にとっても、適切な通院や資料の収集に対応するのは簡単なことではありません。
適切な等級認定を受けたいけど、どのように対応すればよいのかわからず悩んでいるという方は、どうぞ当法人の弁護士にご相談ください。
弁護士法人心は高次脳機能障害について多数の取扱い実績がございます。
また、津にお住まいであれば、津の事務所が津駅から徒歩0.5分の立地にあり、アクセスに便利です。
交通事故の問題解決を得意としている弁護士が、ご相談をお伺いして適切な解決に向けてのサポートをさせていただきますので、津で交通事故に遭い高次脳機能障害が残ってしまった方や、そのご家族の方がいらっしゃいましたら、お気軽に当法人までご連絡ください。
高次脳機能障害と判断される要素について
1 高次脳機能障害と判断される要素は?

交通事故に遭い、高次脳機能障害が残ってしまった方々に、高次脳機能障害と判断される要素についてご説明します。
自賠責保険では、①頭部外傷があること、②一定期間の意識障害が継続したこと、③交通事故による脳の受傷を裏付ける画像上の所見があること、④認知障害、行動障害、人格変性などの高次脳機能障害特有の症状があること、が基本要素となります。
2 意識障害とはどのようなものか
意識障害は、高次脳機能障害と判断するにあたり、非常に重要な要素です。
頭部外傷後、半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態が少なくとも6時間以上継続すると高次脳機能障害が残ることが多く、ここまでは至らなくとも健忘症または軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いた場合も高次脳機能障害を残すことがあるとされています。
3 画像所見とはどのようなものか
CTやMRI等の画像所見のことです。
これは、非常に重要です。
脳室内出血やクモ膜下出血が生じていないか、また、一見正常に見えるとしても脳内に点状出血が生じていないか(びまん性軸索損傷)等を注意深く確認する必要があります。
そして、びまん性軸索損傷による高次脳機能障害の特徴として、脳室拡大・脳萎縮が生じることがあり、3か月程度で固定し、その後はあまり変化することはないとされています。
そこで、慢性期の画像所見として、脳室拡大、脳萎縮の有無を確認することも重要です。
4 高次脳機能障害に特有の症状とは
感情の起伏が激しい、気分が変わりやすい、怒りやすい(大声を出す)、話が回りくどく要点が伝わりにくい、話の内容が変わりやすい、服装や身じまいに無頓着、性的な異常行動や性的羞恥心の欠如、複数のことを並行して同時に作業することができない、周囲の人間関係で軋轢を生じる等が挙げられます。
これらについては、医師の所見だけではなく、日常生活で接する、被害者の生活状況や人格・性格を把握している被害者の家族等が、事故後における被害者の性格や行動の変化を注意深く観察することが必要です。