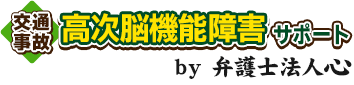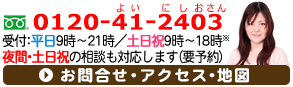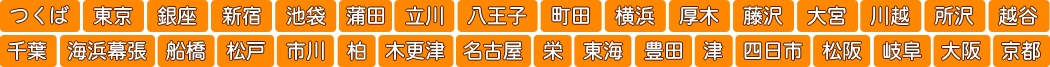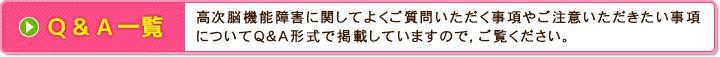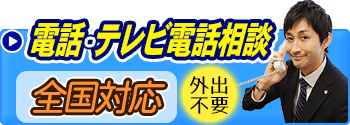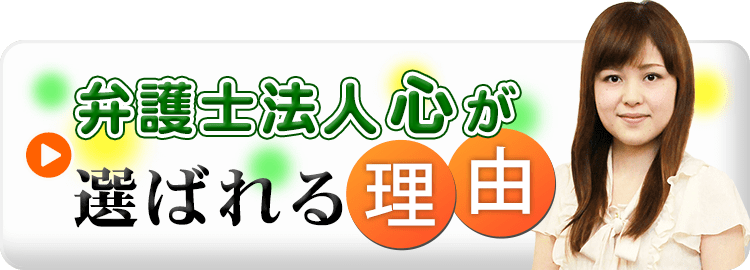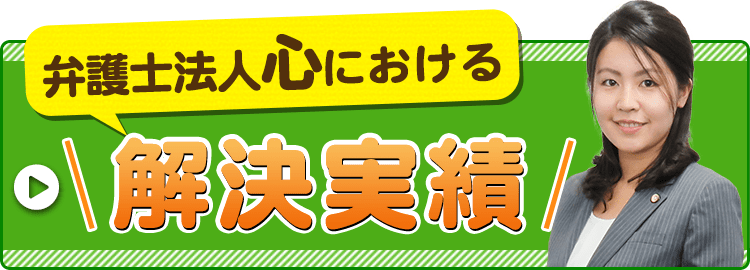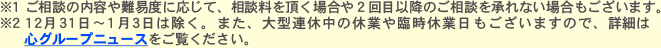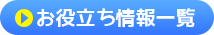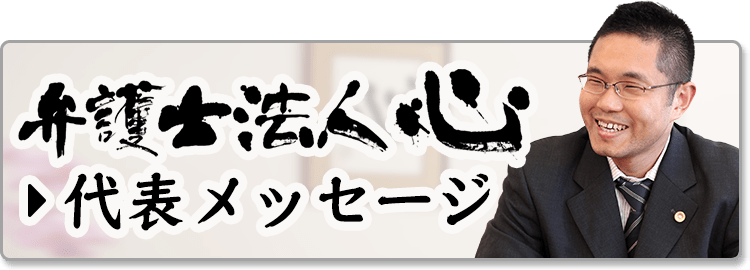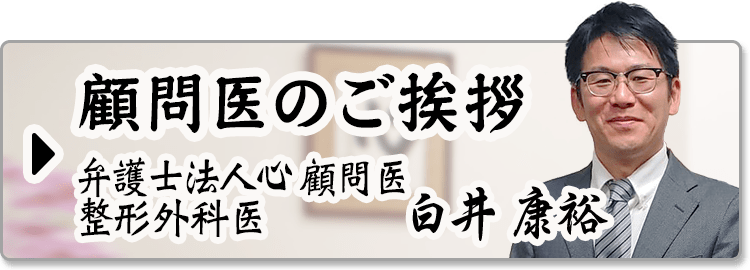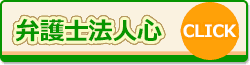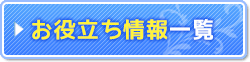「その他の高次脳機能障害情報」に関するお役立ち情報
高次脳機能障害と成年後見
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害は、交通事故や脳卒中などで脳損傷が生じ、脳損傷に起因して認知(記憶・注意・行動・言語・感情など)の障害が起こることをいいます。
障害の内容は、物の置き場所を忘れるといった「記憶障害」、ぼんやりしていてミスが多いといった「注意障害」、人に指示してもらわないと何もできないといった「遂行機能障害」、思い通りにならないと大声を出すといった「社会的行動障害」に分類されることが一般的です。
高次脳機能障害の症状は、本人に自覚がないこともあるため、同居の家族など周囲の方が注意して見守ることが重要となります。
2 高次脳機能障害と後遺障害認定
高次脳機能障害が後遺障害として認定された場合には、第1級、第2級、第3級、第5級、第7級、第9級のいずれかの等級認定がされます。
そして、自賠責保険にて、高次脳機能障害が後遺障害として認定されるためには、少なくとも次のいずれかの状況を満たしていることが必要であると解されています。
- ⑴ 脳挫傷、びまん性軸策損傷、びまん性脳損傷、急性硬膜外血種、急性硬膜下血種、外傷性くも膜下出血、脳室出血等の脳に関する重度の傷病名が確定診断されていること
- ⑵ 上記の傷病名について画像所見が得られていること
- ⑶ 頭部外傷後の意識障害が6時間以上続いていたこと、もしくは健忘症あるいは軽度意識障害が1週間以上続いていたこと
なお、画像については、通常、レントゲン(X線による単純画像診断)では頭蓋骨骨折及び脳損傷を、CTでは脳委縮を、MRIでは脳委縮等を確認することできます。
意識障害の程度を把握するための方法としてJCSとGCSが用いられることが一般的です。
JCSとはジャパン・コーマ・スケールのことをいい、短時間で簡便に意識レベルの評価を行うことができ、間脳・中脳・延髄への侵襲の目安として判定しやすいため、緊急時に用いられます。
項目としては、覚醒している、刺激に応じて一時的に覚醒する、刺激しても覚醒しないという内容で意識障害の程度を把握するものになります。
GCSとはグラスゴー・コーマ・スケールのことをいい、「開眼・最良言語反応・最良運動反応」の3側面の総和で評価するため、やや複雑になり、そのうち1項目でも判定が困難な場合は意味をなさないという問題があります。
以上を踏まえて、意識障害の程度は、おおむね、当初の意識障害が半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態でJCSが2~3桁、GCS12点以下が少なくとも6時間以上継続しているか、健忘症、あるいは軽度の意識障害があり、JCSが1桁、GCS13~14点が少なくとも1週間以上続いていることが確認できる程度のものであることが高次脳機能障害の認定が受けられるかどうかの一つの目安となります。
3 成年後見制度について
成年後見制度は精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人(成年後見人)を付けてもらう制度です。
民法7条に「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。」と規定されています。
成年後見の申立てを行った場合は、家庭裁判所が成年後見人を選任しますが、身近な親族、弁護士や司法書士等の専門家が選任されることが多いと思います。
4 高次脳機能障害と成年後見
高次脳機能障害となった方の中には、事理弁識能力(物事を分別する能力)を欠く状態になる方がいます。
そのような方が、契約内容などを理解しないまま、重要な取引や契約などを結んでしまうと、不利益を被る可能性を否定できません。
そこで、このような場合には、本人の不利益を避けるため、適切な管理者として成年後見人を選任して、成年後見人が本人のために契約締結など行います。
交通事故によって高次脳機能障害になり、本人に事理弁識能力がないような場合には、成年後見制度を用いて、後見人を選任することをお勧めします。
5 高次脳機能障害について弁護士法人心に相談
当法人では、交通事故担当チームをもうけ、高次脳機能障害を含む交通事故案件を集中的に取り扱っております。
また、自賠責保険の調査事務所で後遺障害の認定業務に携わったことのある者も所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制を整えております。
高次脳機能障害でお悩みの方は当法人にご相談ください。
家族が高次脳機能障害になった場合に気を付けるべきこと 高次脳機能障害において緊急搬送時には画像上異常無しと診断された時の注意点
被害者本人だけでは示談できないこともある
1 成年後見制度、保佐制度、補助制度とは

交通事故によって、脳にダメージを受けてしまい、判断能力が不十分(寝たきりや、高度の認知障害、行動障害、性格変化が認められる場合など)になった人のために、家庭裁判所が、その被害者の方の援助者(成年後見人、保佐人、補助人)を選任し、その方を保護するための制度です。
未成年の方は通常親権者がいるため、成年後見申立て等は必要ありませんので、以下は、成人の場合についてご説明いたします。
2 高次脳機能障害の等級
交通事故により、脳にダメージを受けた方は、高次脳機能障害になる可能性があります。
障害の程度に応じて、自賠責の等級は、1級、2級、3級、5級、7級、9級が認定される可能性があります。
3 何級であれば成年後見人ないし保佐人が必要か
あくまでも、高次脳機能障害の被害者の方の状態を主治医の先生が判断して診断書を書き、それをもとに家庭裁判所が最終的に、成年後見人を付すのか、保佐人を付すのか決定します。
何級であれば成年後見人が必要というのは特に決まっていないのですが、当法人のこれまでの経験は、下記のとおりです。
- 1級、2級:成年後見人
- 3級:保佐人
- 5級:高齢者の場合保佐人、20代~40代の方は、不要
- 7級:不要
- 9級:不要
上記は、あくまでも一例であって、必ず上記の通りに判断されるわけではありませんので、ご了承ください。
4 判断能力不十分の被害者本人だけでは終局的な示談はできない
判断能力が不十分な方は、法律上、完全に有効な契約を取り交わすことはできません。
もし、被害者本人だけで示談したとしても、後に、成年後見人、保佐人などが選任された場合などは、成年後見人等に取消権を行使され、被害者本人だけで交わした示談が無効となってしまうからです。
そうである以上、交通事故により判断能力が不十分となってしまった方が、終局的な示談をするためには、原則として、成年後見や保佐申立てをする必要があります。
よく成年後見人や保佐人の業務が面倒だという理由で、それらの申立てをしないでも終局的に示談できる方法はないかと聞かれますが、そのような方法は存在しませんし、成年後見人や保佐人等を付さない状態で、契約を結んでくれる弁護士もいないと思ってください。
5 当法人までご相談ください
当法人では、高次脳機能障害や成年後見申立てなどのご相談についても承っております。
交通事故案件を得意とする弁護士が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。