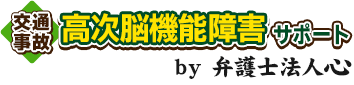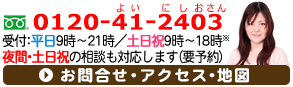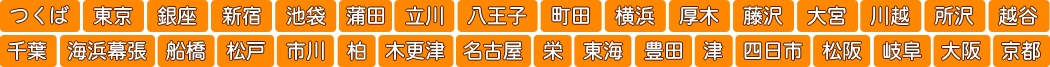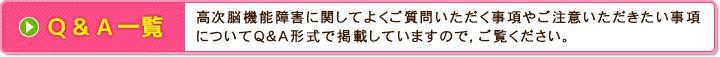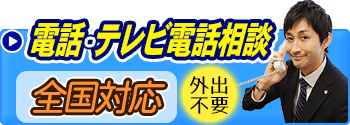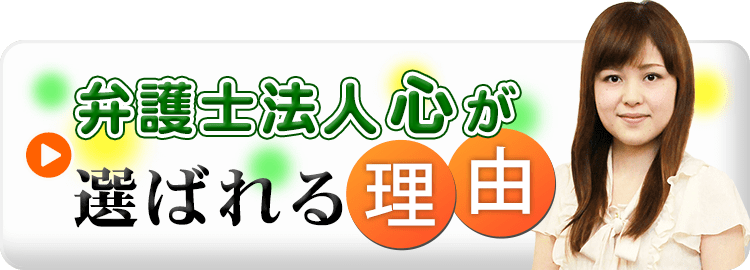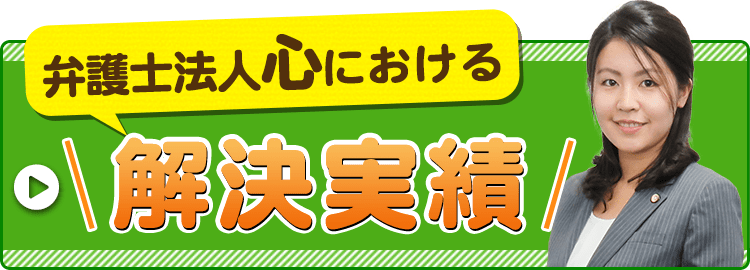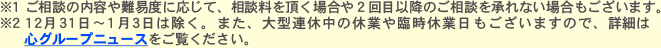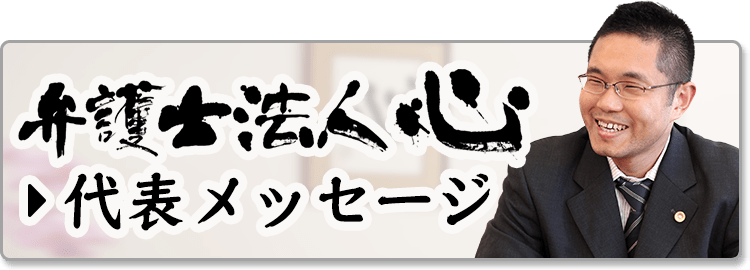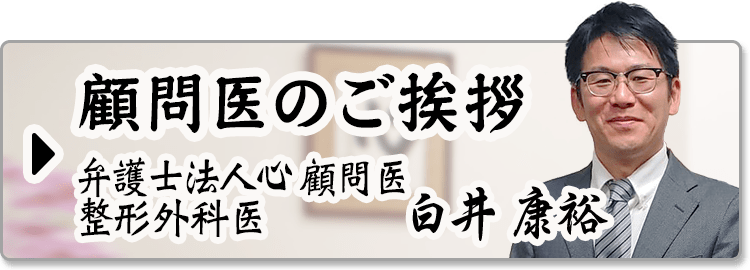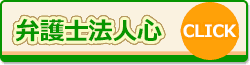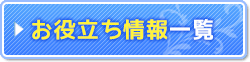「高次脳機能障害の後遺障害」に関するお役立ち情報
高次脳機能障害が後遺障害として認定される判断基準
1 どのような判断基準があるのか
自賠責保険において高次脳機能障害が後遺障害として認定されるためには、高次脳機能障害の典型的な症状とされる認知障害、行動障害等の原因となる脳の器質的損傷が存在することが必要です。
高次脳機能障害は、脳の器質的損傷を伴わない精神障害(非器質性精神障害)とは区別され、①脳の器質的損傷を裏付ける画像検査、②画像所見の評価、③画像所見以外の臨床所見(意識障害、症状経過等)を総合的に判断して認定されます。
2 脳の器質的損傷を裏付ける画像検査
脳の器質的損傷の判断は、CTやMRIの画像が重視されます。
CT上、異常所見が認められなくても、頭蓋内病変が疑われる場合は、事故後、早期にMRIを撮影すると、脳挫傷が明らかになることがあります。
画像検査の結果、脳挫傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫等の脳の器質的損傷を裏付ける診断が得られていることが重要です。
3 画像所見の評価
びまん性軸索損傷の場合は、外傷直後のCTやMRIで頭蓋内病変や脳挫傷が確認できないこともあり、画像上の異常を経時的に把握する必要があります。
MRIで脳内に点状出血等の所見が認められる場合、その後、脳室拡大等の脳萎縮が目立ち、3か月程度で脳室拡大等が固定するものと考えられています。
こうした変化を外傷により軸索が損傷したものと捉えて、脳の器質的損傷を裏付けることができるからです。
4 画像所見以外の臨床所見(意識障害、症状経過等)
高次脳機能障害の症状を判断するためには、画像所見だけでなく、意識障害の有無・程度・持続時間、神経症状の経過、認知機能を評価するための神経心理学的検査も重視されます。
ア 意識障害
意識障害は、脳の機能的損傷が生じていることを示す事情であり、脳の器質的損傷に起因する意識障害が重度で持続が長いほど(特に外傷直後から6時間以上継続するケース)、高次脳機能障害が生じる可能性が高くなります。
イ 症状経過
高次脳機能障害の典型的な症状は、認知障害、行動障害、人格変化です。
これらの症状は、頭部外傷を契機として発現し、徐々に軽減しながら残存するという経過をたどります。
ウ 神経心理学的検査
障害の程度を把握するために、神経心理学的検査、具体的には、WAIS-Ⅲ、WMS-R等の結果も参考にされます。
高次脳機能障害の等級が認定されない場合 高次脳機能障害に詳しい弁護士の見極め方